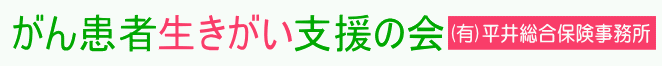『生かされている』と感じた時、奇跡が起きる
「病院に頼らない医療」こそが最先端の医療の著者の渥美和彦(東大名誉教授)は、1954年東大医学部を卒業後、心臓外科医としてキャリアをスタートさせた。1960年代には人工心臓、レーザー治療、電子カルテといった技術を実用化させた。その医療の可能性と限界を知悉した渥美先生の病気に対する私たちへのアドバイスは以下の通りです。
(1)100%医者任せにしないこと〜医者に頼りきりでは、治るものも治らないと言われています。人体というものは、おしなべて医学では到底解明しきれないほど複雑で深遠です。どこまで究めても「わからないこと」、「予測不可能なこと」が必ず出てくる。医療に限界があることを知らないまま、何でもかんでも病院や医者任せにしていると、どうなるでしょうか。当然、治るものも治りませんし、健康そのものに害が出てくる場合さえあるでしょう。ですから、「医者が何でも治してくれるだろう」、「病院に行けばスッキリするだろう」と考えるのは、やめるべきなのです。
では、どうすればいいのか。→①病院で出来ることと、否のこと②医者に任せることと、否のこと③出来る限り、自分で自分の面倒をみる。この3点をキチンと頭に入れて自分の体を養っていく。それが、何より大切です。
(2)「診断」と「治療」は分けて考える。そうすると、どこまでを医者に任せるか、どこからを医者の世話にならずに済ますか、判断できるようになる。これを一緒くたにしたままでは、本来、医者の世話にならずに済むことさえ、だらだらと医者の世話になってしまう。
(a)まず、基本的に「診断」は、全面的に医者に任せるべきです。これを医者以外がやると命にかかわります。
(b)「治療」は、病院に任せきりにすべきではない。医学がどれほど進歩しようが、「医療技術が治す」わけではない。皆さんの体を治すのは、一人ひとりに生まれつき備わっている「自然治癒力」以外の何ものでもありません。要するに、患者さん自身が治していくのです。ですから、自然治癒力を高められるのならば、病院以外の方法もどんどん利用すればいいのです。
(c)a,bを経て、医者から「これこれの薬を出しておきました」と言われる方が、何となく安心する。私はこれについてもはなはだ疑問に感じています。医者から出された薬を飲んでたちまち症状が和らぐと、やはり嬉しいものです。ですが、「よく効く」というのは、考えてみると、恐ろしいことです。体に対して強く作用するわけですから副作用も強く、体への負担がとても大きくなります。正に、両刃の剣なのです。「やめられない薬」は避けるべきなのです。
(d)「思い込み」の力、「プラシーボ効果」は現在の科学ではほとんど重視されていません。ですが、私自身はこの「プラシーボ効果」に積極的な意味を見出してもいいのではないかと感じています。思い込むこと、信じることによって体の状態が変化する。これは現実に起こるのです。
(e)「がん」を不幸と思わない〜一つの受精卵から細胞分裂を繰り返して、60兆個まで増えたのが私たちの体です。この遺伝子は、ウイルス、紫外線、発ガン物質などによって絶えず傷つけられているのですが、「がん抑制遺伝子」、「DNA修復遺伝子」がキチンと働いていればガンにはなりません。
(f)では、ガンとどのように闘っていけばいいのか〜 「心」が重要な役割を果たすのは間違いありません。特に、かなり進行してしまったガンの場合、患者さん自身が自らどういう精神状態にもっていくかが鍵になります。
(g)「生かされている」と気づいた時、奇跡が起きる〜ルルドの泉の話。「自分は宇宙の中に生かされている小さな存在である」と気づいた瞬間に治癒したという話もあります。
(h)「感謝」は一番の妙薬〜人が「生かされている」と感じる時、脳の中では何か爆発的な反応が生じているのかもしれません。
(i)「目に見えないもの」を信じる力〜例えば、末期のガン患者さんで、「助かるまい」と思っていた方であっても、10万人に一人位の確率で自然に治ってしまうことがあります。気の遠くなるような確率ですが、それは本当に起こるのです。いったい何が効いたのか、どのような作用が起こったのか、科学的に説明できる点は一つもない。目に見えてみんなが納得できる要素は皆無であるにもかかえわらず、です。要するに、「目に見えないもの」が病気を消してしまったわけです。人工心臓の研究に取り組んでいた頃のことです。私たちは、人工心臓を体に埋め込んだヤギを研究室で飼って、生存日数の世界記録に挑んでいました。
人工心臓といえば、正に、未来を変える最先端の分野でしたから、研究室総出で文字通り命を賭けて取り組んでいました。そして、いよいよ世界記録の達成なるかという瞬間、「目に見えないもの」の力が私たちを包み込み、しっかりと守ってくれているのを感じたのです。私、スタッフ、ヤギ、そしてその場にある種々の機械・・・。
あらゆる存在が一つになって、神々しいエネルギーを放っていました。今でも思い出すと体が震えるほどの圧倒的な力でした。「宇宙との一体を覚えた」そういう感覚でありました。
超システム
免疫学の多田富雄先生は、生物の持っている不思議なシステムを超システムと名付けられました。生物の生体内での物質のやりとりを総称して「物質交代」(metabolism)もしくは、「代謝」といいます。物質交代の中心は、「酵素」(enzyme)です。生命体を作り出す時、たくさんの遺伝子が働いて多様な細胞が生み出されます。そして、それらが、お互いに情報交換することによって次々に新しい段階のものを作り出していく。つまり、自分で自分を作り出すというプロセスがある。これらは、私の体内で無意識のうちに行われています。生命の本質である「自己複製」と「物質交代」の中心にゲノムがあり、遺伝子があります。工学的な「複製」は、多様な要素を目的のために組み合わせて、それが有機的に動いていくけれど、生命体の場合は、初めから多様な要素があるわけではありません。多様な要素は自分で作り出していく。自分で作り出して、それがお互いにつながり合って自己組織化をする。 最終的には全体としてうまくいくようなものを自ら作り出していく。その過程で不要なものは、どんどん死んでいく。これも、私の体内で無意識のうちに行われています。これは、設計図に従って機械を作って、その機械が動いたり壊れたりするのとは違うものです。このようなことが、私の意識を離れて行われています。このことを、多田先生は「超システム」と名付けられました。超システムによって、私の哲学思考は工学的なことに気づかされました。つまり、私の哲学思考は、コピー機だったのです。コピー機がコピー機を生み出して、初めて「自己複製」と言える。以下は多田先生の受け売りです。→哲学は、数千年にわたって「人間とは何か」とか「生命とは何か」という問題を考えてきたが、そこには、基本的に科学がなかった。これからは、生命科学、つまり、ゲノムやそれを基礎にした人間というものを知らずしてこれからの哲学は成り立たないと思う。一方、生命科学も、どんどん発展するでしょうが、非常に危険な部分を持っています。例えば、「脳死」、脳は死んでいても、身体は生きているから移植が出来る。これからは、尊厳死とか終末期医療などに関連して「積極的に生命を断つ」医療の場面が次々と出て来ると思います。生命を持つ個体の内部では、次々と細胞が死に、再生し続けています。固体の生命とは、構成要素である細胞の総和ではなく、「自己同一性」に裏付けられた「超システム」の活動として理解しなくてはならない。20世紀とは科学がおおもとの問題を見失った時代です。それを言い換えれば、科学を主導する思想や夢がなくなってしまったということです。21世紀、私たちは、もう一度、人間が人間として生きていくための根源的な問題を再発見しなくてはなりません。